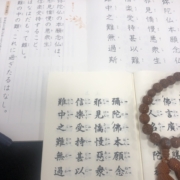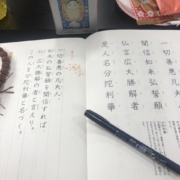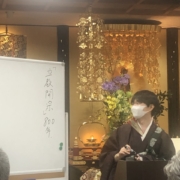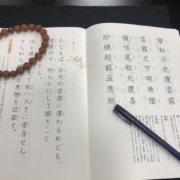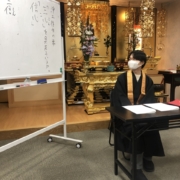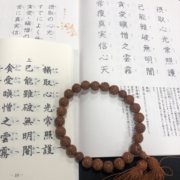前回で「正信偈」を一通りたずね終えたということで、本日からは『仏説阿弥陀経』の書写をしていきます。初回ということで、『阿弥陀経』について少し見ていきますと、真宗では浄土三部経と呼ばれる『大無量寿経』・『観無量寿経』、そしてこの『阿弥陀経』(『小経』)を具体的には言って、大事な聖典としております。親鸞聖人はその浄土三部経を『大無量寿経』を真実の教とし、『観無量寿経』と『阿弥陀経』は方便の教として見ておられます。方便というとつまらないものだと思われるかもしれませんが、方便はとても大事なのです。方便があってはじめて真実に触れるということがあるわけです。その方便の教である『仏説阿弥陀経』は「無問自説経」とも呼ばれます。経典の多くはその経典が説かれることになった背景、「発起序」というものが描かれます。例えば『観無量寿経』では王舎城の悲劇が描かれますが、経典が説かれるきっかけとなる大事な問いがこの『阿弥陀経』にはありません。釈尊が智慧第一の舎利弗に対して、舎利弗よ舎利弗よと言ってずっと語っていかれます。普通はどうですか?という問いに対して、釈尊がお答えになるという形ですが、舎利弗が問うことはありません。なので『無問自説経』と呼ばれます。
この『無問自説経』ということを親鸞聖人は、釈尊の出世本懐の経だと押さえられます。出世本懐ということは、この経を説く為に釈尊はお生まれになったという意味です。それほどこの『阿弥陀経』は大事なことを語っているのです。ここにある「恒沙の諸仏の証護の正意」ということは追々尋ねていきますが、誰に向かってその本懐を語っているかを今日は注目します。
釈尊が阿弥陀経を説かれた場所は「祇樹給孤獨園」です。祇園精舎という呼び名が有名ですが、祇園精舎というのは、須陀多という長者に護られている精舎で、須陀多は孤児や独老など身寄りのない、一人では食べていくこともできない人々に手を差し伸べた方で、釈尊が説かれた阿弥陀経は、辛い生活をされていた方も聞いていたでろうことが想われます。その証拠に、この祇園精舎に集った有名な菩薩様に加えて、「無量の諸天・大衆と倶なりき。」と敢えて言って、大衆という一般市民も一緒に教えを聞いていたと書いてあります。菩薩とともに多くの大衆が一緒に聞いている。つまり、釈尊は優秀な者だけでなく、むしろ俗世に苦しみ生きる者たちに向かってこの阿弥陀経を説いているのです。そのことが、出世本懐の経と親鸞聖人が捉えた一因でもあるように思います。…